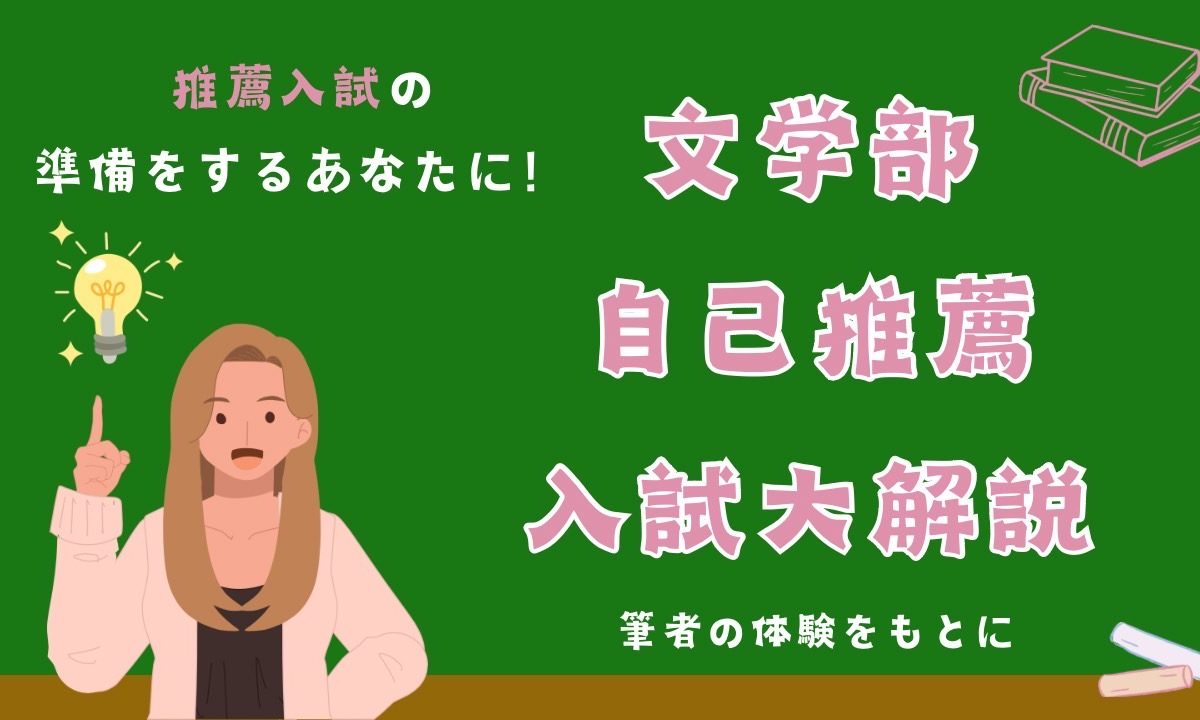
目次
今回も自己推薦について筆者の体験をもとにご紹介していきます!!
試験の内容やどのような対策をしたかについて書いていくので少しでも参考になればとても嬉しい次第です、、
あくまでも個人的な話にはなってしまいますが、私が自己推薦を受験しようと決め、対策をはじめたのは高三になったばかりの4月でした。
もともと推薦入試は面接が大変そうだなというイメージから利用する予定はありませんでしたが、この慶應文の自己推薦入試は世にも珍しい面接を行わない推薦入試なんです!主に小論文で合否を決める入試のようです。
倍率が低い穴場な入試方式ということもあり、チャンスを増やすためにも受けてみることにしました。
実際どのような小論文対策をしていたのか説明します!
高三4月頃から週に一回過去問をとき、慶應文の小論に詳しい高校の先生(この先生に教えていただいたことが一番の合格の理由です)に添削してもらいました。
スケジュールとしては4月から8月の間に総合考査Ⅱ、9月から11月(結構ギリギリでした汗)の間に総合考査Ⅰを2011年度から2023年度の13年分解きました。
1番重きを置いて対策して欲しいのが総合考査Ⅱです。
問題文が短くシンプルな分、どのような回答を書けばいいのか選択肢が多く私自身かなり苦戦しました。字数内で主張とそれを補強する具体例、そして結論を矛盾なくまとめる能力も問われます。
まず、注目してもらいたいのが課題文のタイトルです。正直、課題文がとても短いのでそれだけでは全然意味がわからないという可能性もありえますが、タイトルに重要なキーワードが書いてあることがとても多いです。
そして、少し難しいですが回答を作る上で課題文の内容から探してみて欲しいのが“目に見えないもの”です。感情やマイノリティーな存在などいろいろあります。
人文社会学科というだけあって扱うテーマは様々ですが目に見えないものが高確率で出てきます。それを文学部としてどのように扱うのかという視点で考えると出題者側の意図も見えてくるかもしれません
総合考査Ⅰでは長文の課題文を読み、文章に関する問題を2題と指定された文章を英訳する問題を2題解きます。
こちらの問題は課題文をもとに回答を作成するのでほぼ要約に近い感じです。自分の意見を求められるわけではないので、総合考査Ⅱに比べて書きやすいのではないかと思います!
時間との勝負になるので、まず最初に問いをみて何を書かないといけないのか把握してから文章を書き始めることを強くお勧めします。ここを回答に使いたいという部分は印をつけておいてくださいね!!
英訳に関しては私もあまり自信がなく、配点も高くないだろうということで少し捨てていた部分は否めませんが、単語がわからなくても文構造があっていれば少しはマシになると思うので、どんどん部分点狙っていきましょ
いかがでしたでしょうか?
次回で自己推薦についての記事は最後になります。最終回は試験当日の流れについてご紹介します!!
各SNSで新入生や大学生の役に立つ情報を発信しています!
わからないことがあれば気軽に各メディアからご連絡ください🙌
イベント情報の発信や申込み、お役立ち情報が見られます!